国立競技場は、日本のスポーツと音楽の歴史を象徴する場所です。
2005年にSMAPが初めてライブを行って以来、嵐、L’Arc〜en〜Ciel、ももいろクローバーZ、矢沢永吉など、時代を彩るアーティストたちがステージに立ちました。
2019年に完成した新国立競技場でも、Adoをはじめとするアーティストが新たな歴史を刻んでいます。
本記事では、旧国立から新国立までの歴代ライブアーティストや、公演の特徴、さらに最新の演出技術による未来像まで徹底解説します。
国立競技場でライブを行った歴代アーティスト一覧
日本において「国立競技場」といえば、スポーツだけでなく音楽シーンの舞台としても特別な意味を持つ場所です。
旧国立競技場では2005年から2014年にかけて数々のアーティストが歴史的なライブを行い、その記憶は今もファンの心に刻まれています。
そして2019年に完成した新国立競技場でも、徐々に音楽ライブが実施され始めています。
ここでは、旧国立から新国立までの歴代アーティストとその特徴的な公演を振り返ります。
SMAP ― 国立ライブの先駆者
2005年に初めて国立競技場でライブを行ったのがSMAPです。
アイドルグループとして初の快挙であり、翌2006年にも続けて開催。国立でのSMAP公演は、アイドルグループがスタジアム規模で社会現象を巻き起こすことを証明した出来事でした。
その後のジャニーズグループや他アーティストの国立公演にも大きな道を開いたと言われています。
DREAMS COME TRUE ― J-POPの重鎮が残した軌跡
2007年にはDREAMS COME TRUEが国立のステージに立ちました。
安定した歌唱力と壮大な演出で観客を魅了し、ポップスグループとしての存在感を改めて示しました。
「未来予想図」や「何度でも」といった名曲がスタジアムに響いた夜は、多くのファンにとって忘れられない思い出となっています。
嵐 ― 国立=嵐と呼ばれる黄金時代
2008年から2013年にかけて6年連続で国立競技場ライブを開催したのが嵐です。
合計15公演という数字は前人未到であり、国立競技場=嵐というイメージを確立しました。
2013年の閉場前最後のライブも嵐が飾り、2020年には新国立競技場で無観客ライブを実施。ファンの間では「嵐の国立」として語り継がれています。
L’Arc〜en〜Ciel ― ロックバンドの存在感
2012年と2014年にはL’Arc〜en〜Cielが国立に登場。
特に2014年の公演は大規模な動員を記録し、圧巻のステージ演出とともに語り草となっています。
ビジュアル系シーンから世界的なロックバンドへと成長したラルクにとって、国立でのライブはキャリアの大きなハイライトの一つでした。
ももいろクローバーZとAKB48 ― 女性グループの挑戦
2014年は国立競技場の閉場を控えた特別な年でした。
この年、ももいろクローバーZが女性グループとして初の単独公演を開催し、アイドルシーンに大きな足跡を残しました。
さらにAKB48も単独ライブを行い、女性アイドルが国立の舞台に立てることを証明しました。これらは女性アーティストの活躍を象徴する出来事といえるでしょう。
矢沢永吉 ― 新国立でのロックレジェンド
2019年に新国立競技場が完成し、音楽イベントとして注目を浴びたのが2022年の矢沢永吉の公演です。
日本のロック界を代表する存在が、新国立で観客を熱狂させたことは、「新しい国立の幕開け」を象徴する出来事でした。
Ado ― 次世代を担うシンガー
2024年にはAdoが新国立競技場でライブを開催。YouTube発のアーティストとして、ここまで到達したのは異例の快挙です。
圧倒的な歌唱力とデジタルを駆使した演出で、従来のスタジアムライブとは一線を画す体験を提供しました。SNSを中心に大きな話題となり、「新国立の歴史に新しいページを刻んだ」と評価されています。
このように、国立競技場は旧・新を通じて日本の音楽史において特別な場所であり続けています。アイドル、J-POP、ロック、そして次世代シンガーと、ジャンルを越えたアーティストが舞台に立つことが、その存在の大きさを物語っています。
新旧国立競技場のライブ環境と特徴の違い
国立競技場は、日本のスポーツと音楽の両方における象徴的な舞台です。
しかし、旧国立競技場(1964〜2014年)と新国立競技場(2019年〜)では、その設計目的や設備が大きく異なり、ライブ体験にも違いが生まれています。
ここでは両者の特徴を比較しながら、ファンが感じる魅力や課題を整理してみましょう。
旧国立競技場 ― 音楽の「聖地」としての役割
旧国立競技場は1964年の東京オリンピックに合わせて建設され、主にスポーツ会場として使用されていました。
しかし2000年代半ば以降、音楽ライブの舞台としても脚光を浴びます。特に2005年以降、SMAPや嵐をはじめとした人気アーティストが立ち、「国立のステージに立てることが名誉」とまで言われるようになりました。
当時の設備は音楽専用ではなく、音響面での制約はありました。
それでも、観客が一体となる雰囲気や、広大なスタジアムを埋め尽くす光景は他に代えがたい魅力でした。嵐の連続公演やラルクの大規模ライブなどは、今でも「伝説の国立ライブ」として語り継がれています。
新国立競技場 ― 最新設備と課題
2019年に完成した新国立競技場は、東京2020オリンピック・パラリンピックのメイン会場として設計されました。
そのためスポーツ観戦に最適化されている一方で、音楽ライブではいくつか課題も浮き彫りになっています。
音響の課題が最も大きなポイントです。スタンドの広さや部分的な屋根構造の影響で音が反響し、歌詞が聞き取りにくいという声があります。
音の遅延やこもりが生じやすく、クリアな音質を求めるファンからは改善を望む声も少なくありません。
一方で、新国立競技場ならではの魅力も多くあります。最大収容人数は約8万人と国内最大級であり、一度に大規模な観客を収容できる点は大きな強みです。
また、広大な空間を活かした映像・照明演出は圧巻で、観客全体を巻き込むスケール感が楽しめます。特にAdoの公演では巨大スクリーンや特殊照明が駆使され、新時代のスタジアムライブを象徴する演出が話題になりました。
観客体験における違い
ライブを楽しむ観客目線では、入退場や座席の見え方にも両者の違いがあります。
- 旧国立は段差の少ない座席配置で、一体感を感じられる反面、後方席からはステージが見えにくいという声がありました。
- 新国立はスクリーンの活用が進み、遠方の席でも演出を楽しめる工夫がされていますが、アリーナ席では前方の観客で視界が遮られることも。
さらに、8万人規模の動員を誇る新国立では、入退場の混雑が避けられません。特に開演前と終演後は大きな人の波が生まれるため、早めの行動や事前の交通手段の確認が重要です。
「聖地」としての継承
旧国立が築いた「音楽の聖地」としての歴史は、新国立にも確実に受け継がれています。
嵐が2020年に無観客でライブを行ったのも、国立という場所に特別な意味があるからです。矢沢永吉やAdoの新国立公演も、単なるコンサート以上に「新しい歴史の一幕」として記録されました。
つまり、旧国立は「伝説を刻んだ舞台」、新国立は「未来を切り拓く舞台」として、それぞれ異なる役割を果たしているといえるでしょう。
新国立競技場が切り拓くライブ演出の未来
新国立競技場は、単なるスポーツ施設にとどまらず、テクノロジーとデザインを融合させた次世代型スタジアムとして注目を集めています。
2019年に完成して以降、音楽ライブの舞台としてはまだ限られたアーティストしか立っていませんが、その演出面には大きな可能性が秘められています。
ここでは、新国立競技場が実現する未来型のライブ演出について詳しく見ていきます。
データ活用による映像演出
新国立競技場の強みの一つは、データを活用した演出技術です。
東京2020パラリンピック開会式では「The Wind of Change」をテーマに、各国の国旗や音声データをもとに生成された映像を投影しました。
流体シミュレーションを用いたこの演出は、国ごとに異なる“風”を表現し、観客に強烈な印象を残しました。
この仕組みを音楽ライブに応用することで、楽曲ごとにカスタマイズされた映像や、観客の反応をリアルタイムに反映した演出が可能になります。
例えば、SNSの投稿や観客の動きをデータ化し、ライブ中に映像演出へ取り込むなど、観客が演出に参加する新しい体験が生まれるでしょう。
照明技術の進化
新国立競技場はLED照明を効果的に採用しており、従来の照明に比べて演出の自由度が飛躍的に高いのが特徴です。
漏れ光が少なく、スタジアム全体をダイナミックに照らすことが可能です。これにより、曲の世界観に合わせたドラマチックな光の演出や、観客席全体を巻き込んだパノラマ的な照明効果が実現します。特に大規模アーティストの公演では、光と映像を組み合わせた没入型の体験が期待できます。
スマートスタジアムとしての進化
国立競技場は「スマートスタジアム」をコンセプトに掲げており、次世代の通信技術や大画面設備を導入しています。
これにより、観客は自分のスマートフォンを通じて演出に参加したり、ARやVRを活用したコンテンツを楽しむことも可能です。
将来的には、観客一人ひとりにパーソナライズされた体験を提供できる仕組みが整うと考えられます。
また、リアルタイムでのデータ収集と分析により、観客の好みに応じた演出の微調整ができる点も魅力です。
たとえば「盛り上がりがピークに達した瞬間に花火を打ち上げる」といった、ライブ中の即時対応も実現可能になるでしょう。
環境に配慮した演出と快適性
新国立競技場は、木材を多用した設計や自然換気を取り入れるなど、環境に配慮した構造を持っています。
これにより、観客は快適に過ごしながらも自然との調和を感じられる空間が広がっています。演出においても、自然素材とデジタル技術の融合が新しい表現方法を生み出し、サステナブルでありながら感動的なライブ体験を可能にしています。
観客体験の未来像
これらの技術革新は、単に派手な演出を行うだけでなく、観客の記憶に残る特別な体験を提供するためのものです。
データを活用することで観客ごとに異なる感動を届けられ、ARやVRを通じてステージに“入り込む”感覚も得られるでしょう。
さらに、演出の効果を数値化し、次の公演にフィードバックすることで、常に進化し続けるライブが実現します。
新国立競技場での音楽ライブは、過去の「国立ライブ」の伝統を受け継ぎながら、テクノロジーによって新しい歴史を作り出しているのです。
今後、どんなアーティストがここに立ち、どのような革新的な演出を見せてくれるのか、多くのファンが期待を寄せています。
まとめ
国立競技場は、選ばれたアーティストだけが立てる特別な舞台であり、ライブ史に残る瞬間を数多く生み出してきました。
旧国立では嵐の6年連続公演をはじめ数々の名ライブが行われ、新国立では最新技術を駆使した演出が導入され、音楽体験は新しいステージへと進化しています。
音響の課題や座席環境など注意点もありますが、約8万人を収容するスケールと革新的な演出はここでしか味わえません。
今後も新たな歴代アーティストが登場し、国立競技場のライブ史はさらなる輝きを増していくことでしょう。
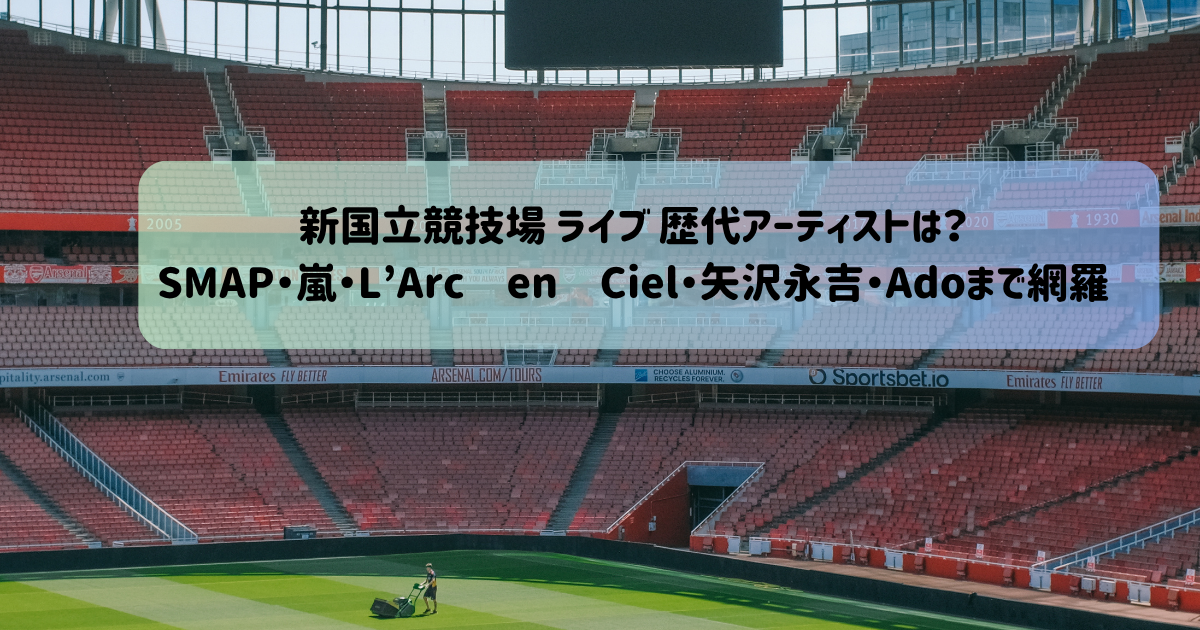









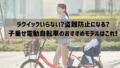
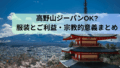


コメント